<<筆者が描く理想の英語教育政策Vision>>
◆ 小学校での外国語(英語)教育:
・12歳(臨界期前)までの生徒に対する英語教育であるため、音声インプットを重視して、日本語/英語のバイリンガルになる素養を創る。少なくとも、英語の基礎発音は、ネイティブレベルを実現する。英語に対して抵抗がなく、英語を第二言語としてではなく、第二母国語として扱う感覚を育てる。
・英語以外にも、多言語/多文化に触れる教育を行い、国際感覚と、異文化を受け入れる寛容な心の状態を育てる。
※筆者自身、趣味のダンスを通じて、児童施設を訪問し、ダンスを教えていたんですが、そこで、ハーフ(ダブル/ミックス)の子が日本社会になじめていない事実を目の当たりにしています。彼らは、自分がハーフだということを隠すために、自分の名字を言いたがりません。そんな現状があります。そういった問題を解決するためにも、また、日本人が国際人として世界で活躍していくためにも、多文化を受け入れる素養を、教育で養ってあげることは大切なことだと感じています。
 ◆ 中学校での外国語(英語)教育:
◆ 中学校での外国語(英語)教育:
・小学校で涵養した基礎発音をベースとして、さらにリスニング重視の教育を行い、英語の音声に対する基礎リスニング力を身につける。並行して、基礎文法/基礎単語力を向上することで、リスニングにおける理解能力も高めていく。今まで通りのリーディングも行うが、決定的に違うのは、生徒全員が、音読時にネイティブ並の発音で行える点。ライティング/スピーキングなど、アウトプットの実践は、高学年になるにつれて時間数を徐々に増やして行くが、中学では、小学校と同じく、インプット重視の教育を行う。
 ◆ 高校での外国語(英語)教育:
◆ 高校での外国語(英語)教育:
・高校では、実践的英会話/文章を書くといったアウトプット重視の授業を行い、中学で身につけた4技能をさらに磨き上げる。第二母国語として、英語で不自由なくコミュニケーションがとれる(会話や文章/メールでのやりとりができる)レベルに達する。
 ◆ 大学での外国語教育:
◆ 大学での外国語教育:
・高校卒業時点で、生徒全員が英語をマスターしており、全員がバイリンガルなので、大学では、英語自体を学習する必要はなく、英語「で」、講義を受けることが可能となる。
・また、大学4年間を通して、小中高校の英語学習で体得した言語の学習方法(ノウハウ)を使い、第三言語をマスターする。
※仮に大学全入時代を想定すれば、、、22歳までの日本人が全員トリリンガルになっている。また、その教育体制が、100年続けば、成人した日本人はみな、3カ国語以上話せる状態になる。
以上が、日本人全員Trilingual計画の概略です。
<<この計画を実際に実現するための問題点とその解決案>>
問題1。ノウハウの問題:
・小中高における、教師が使用する、英語教授法のノウハウの策定が必要。
※CLAメソッドは、成人した人(臨界期を迎えた人)向けのメソッド(ノウハウ)なので、子ども向けのバイリンガル教育には不向き。
解決案:
・第二言語習得(SLA)研究に従事している研究者、それを実践している教育者を招集し、インプット
/コミュニケーション重視した、12年間にわたる英語教育課程のベースとなるノウハウを導きだす。
Ex. インターナショナルスクール等で行われているイマージョン教育(英語での授業)での成功例をもとに、インプットの質や量、教材の選定を行う。
※現行の英語教育は、英語教授ノウハウが、戦後英語教育のままストップしてしまってる(読解中心)。この状態で、小学校での英語学習時間を増やしても効果があまり期待できない。いわば、支点が効いていないのに、力点における力をいくら増やしても、意味がない(作用点における英語能力向上に寄与しない)状態と同じこと。まず、ノウハウという支点を、がっちり固めることが大事。
問題2。体制の問題:
・ノウハウ策定委員会の設置/SLA専門家やSLA実践教育者の招集、TOEFLを大学入試要項に入れるなどの会話重視の外国語教育政策(社会的気運作り)、法的整備、予算などの問題。
(
※2021年からセンター試験を廃止し、その替わりとしてTOEFL/英検をベースにした試験を導入予定とのこと。日経新聞10/25/2014朝刊より)
解決案:
・ここは文科省官僚ならびに政治家の方々の力が必要。
問題3。体制移行の問題:
・当然、いきなりの体制変更ではなく、段階的な移行が現実的。
・仮に、ノウハウが完成しても、それを実行できる教師がいない。
・その教師として外国人(英語ネイティブ)を採用するのは、インプットとしては理想的だが、ノウハウ履行能力とは相関はなく、むしろ、既存の日本人英語教師の英語力が上がり、ノウハウへの理解と実行力を向上させる方が現実的。(新しく人員確保するよりも、コストも抑えられる。)
しかし、、、
・現行の英語教師は、読解中心の教職課程を経ているため、端的に、英語でコミュニケーションをとる能力をほとんど備えていない。発音も日本語発音のままの場合が多く、ネイティブレベルに達している教師はほとんどいない。
※水泳を例にとれば、水泳のフォーム(英語の発音)がバラバラな水泳の講師に習ったら、生徒もフォーム(英語の発音)がバラバラになるのは当然。それが現状であり、教室での音読などで、英語をちょっとでもうまく発音しようとすると、「あいつはネイティブぶってる(笑)」と揶揄される、おかしな学習環境を生んでしまっている。
解決案:
・現行の教師を、各都道府県ごとに招集し、1年かけて、CLAメソッド(=成人用英語教授ノウハウ)を用いて、英語の基礎発音力と、流暢なコミュニケーション能力を磨き直す。それから、文科省がSLAベースで策定した学校での教授ノウハウの実践訓練も積む。(
※水泳で言えば、教師のフォームをまず正す段階。)
・さらに、英語教師の教職過程において、大学生を対象に、教育実習期間の前の1年間、国から給与を付与しつつ、「集中英語涵養期間」を設け、CLAメソッドを用いて、英語教師になりゆく大学生に、流暢なコミュニケーション能力を身につけさせる。と同時に、英語教授方法のノウハウの実践訓練も積んでおく。

・訓練を受けた後、それぞれの英語教師が、各学校に戻り(新しく赴任し)、流暢になった英語と、新しい英語教授ノウハウを、頭がスポンジ状態の生徒に教授する。そうすれば、生徒の英語も流暢になり、英語でのコミュニケーション能力も向上していく。

・そして、その体制が、先述の理想の状態に近づけば、生徒全員が、高校卒業時には、バイリンガルになる。そうなれば、大学時には、英語をマスターしたノウハウと、英語をベースにして、3つ目の言語をマスターすることができ、「大学卒業時には、基本的に全員トリリンガル」という時代を創造することができる。
っとまぁ、ここまで大掛かりな政策は厳しいとしても、、、
コミュニケーション(英会話)がさらに重宝される時代に入り、「英語教師が英語で会話できない/発音が流暢ではない」、、、という状況は、言語的にも教育的にも由々しき問題であり、2020年の東京五輪も考慮すれば、早急に変革が求められているのは間違いありません。
2020年の東京五輪にむけて、舛添知事が以下のようなビジョンを提示しました。
(
※日経新聞9/13/2014朝刊より)
◆681万人(2013年)から、2020年には、1500万人に外国人旅行者倍増計画
◆外国人おもてなし語学ボランティア3万人を手配
◆世界一の都市・東京
「世界一の都市・東京」を目指すなら、都内各地で英語が通じるのは当然のことです。また、英語が話せるボランティアが、そもそも3万人もいるのかどうかも不明です。せめて、2014年の時点での小学生/中学生/英語学科の高校生だけでも、英語が話せるように教育体制を抜本的に見直し、彼らに学生ボランティアとして東京五輪に協力してもらうような流れができれば良いのではないでしょうか。




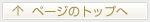

 海外旅行
海外旅行 海外生活
海外生活 受験英語
受験英語 字幕ナシで映画
字幕ナシで映画 TOEIC
TOEIC ビジネス
ビジネス TOEFL - iBT
TOEFL - iBT 学術論文
学術論文 口説きたい
口説きたい